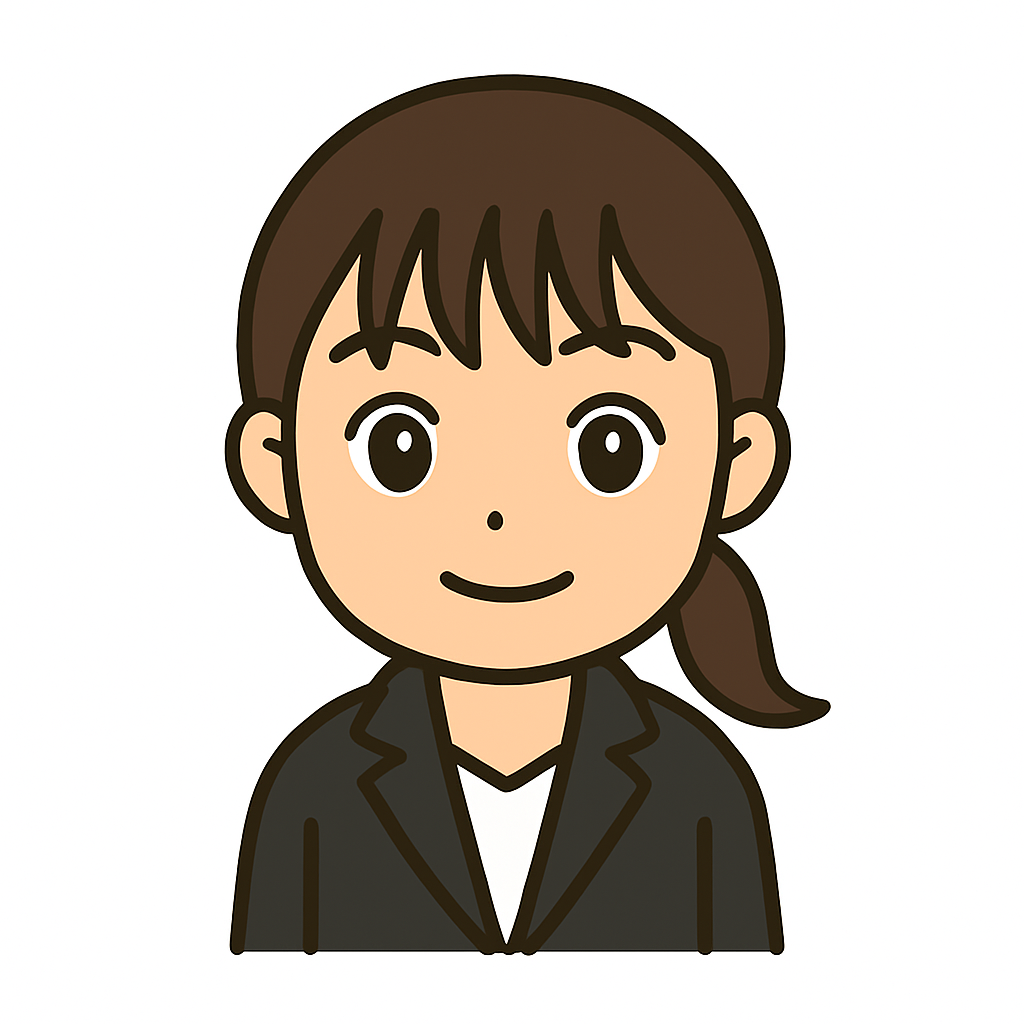こんにちは、丸月瑠奈です。ビル管理の現場では、「言った・言わない」や「どれが最新の契約内容か?」という混乱が積み重なると、クレームの火種になりかねません。例えば、オーナー様から「作業時は必ず養生を二重に」という注意が、複数の人を介在する口頭伝達では正確な伝達ができなくなり、結果的に「丁寧に養生」となって協力会社に伝わり、エレベーターホールに細かな傷を発生させてしまったといった話も聞いたことがあります。こうした小さなニュアンスのズレや契約情報の共有漏れが、大きな信用の損失に直結します。 このコラムでは、そうした情報ギャップの構造とリスクを整理し、DK-CONNECT BMでどう仕組み化できるのかをご紹介します。
ビル管理の指示伝達における問題点
ビル管理の指示は多段階で流れます:オーナー/管理会社→貴社/本社担当→所長→現場責任者→作業実施者→協力会社。この流れの中で起こりがちな課題は次の通りです。
- 媒体分散:口頭・メール・チャット・紙の指示書…情報が散らばり、最新版がわからなくなる。
- 文脈欠落:指示の背景や意図が不明確で、現場で省略や誤解が発生する。
- タイミング不一致:共有はしたが、作業直前に読まれていない。
結果として、「注意事項の見落とし」や「協力会社への伝達漏れ」「引継ぎ時に情報が消える」などが発生し、クレームや再作業につながります。
情報ギャップにより発生するリスク
情報ギャップを放置すると、以下のようなリスクが生じます。
- 直接コスト:再訪問・追加養生・補修対応・違約金が発生。
- 機会損失:次回の入札や増改築の相談から外れる。
- 安全リスク:特に高所や電気設備作業での注意・指示抜けは、事故に直結。
- 組織疲弊:情報の伝達ミスが続くと、現場のモチベーションと離職率に影響。
- 説明責任の不全:監査や是正対応で「誰に何をいつ伝えたか」を示せず、改善が個人任せになる。
これらのリスクは、人の善意や記憶に依存した運用に起因しています。だからこそ、仕組みで情報の抜けを防ぐことが必要です。
DK-CONNECT BMで伝達事項を一元管理
1. 物件ごとに「単一の真実」を置く
各建物ページに、オーナー指示や社内で共有すべき注意点を一元登録し、関係者は誰でも同じ場所を見に行けば最新版の情報を確認できます。季節要因(花粉飛散時は外気取入を調整、イベント日は搬入経路変更など)も物件単位で蓄積でき、引継ぎ時も文脈ごと渡せます。
2. 「読むべきタイミング」を自動でつくる
あらかじめ連絡事項・注意事項を登録しておくと、作業前日に実施者へ自動でメール通知できます。さらに、アカウントを持たない協力会社にも共有可能なため、外部も含めて「前日の最終確認」を徹底できます。
3. 運用のコツ(現場で効く小ワザ)
- 注意事項は目的→具体行動→NG例の順で短文化:例:目的「床保護」→行動「二重養生・端部テープ止め」→NG「シングル養生のみ」。
- ラベル運用で優先度を明示:例:「必須」「要確認」「季節」。
- 定期作業はテンプレ化:毎回の自動通知に添付し、オンボーディングにも活用。
まとめ
情報ギャップは「気をつける」だけでなく、「仕組みで配置する」ことが重要です。情報の場所を一つに、タイミングを自動化し、履歴を残すことでクレームの根を断ち、現場を迷子にしません。DK-CONNECT BMを活用して伝達をシステム化し、情報の伝達ミスによるクレームリスクを無くしましょう。

 製造業向けITソリューション
製造業向けITソリューション 品質DX支援 QX digital solution
品質DX支援 QX digital solution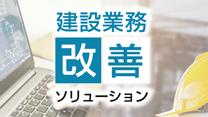 建設業務改善ソリューション
建設業務改善ソリューション ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM
ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM FILDER SiX TOP
FILDER SiX TOP FILDER SiX 電気 TOP
FILDER SiX 電気 TOP Rebro D TOP
Rebro D TOP 実験記録をデータベース化 ParsleyLab
実験記録をデータベース化 ParsleyLab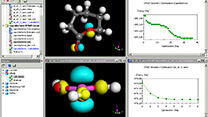 マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio
マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio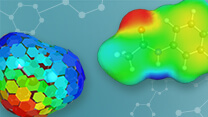 熱力学物性予測ソフトウェア COSMO
熱力学物性予測ソフトウェア COSMO 電子実験ノート
電子実験ノート 総合3DCG 制作ソフトウェア Maya
総合3DCG 制作ソフトウェア Maya 総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max
総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max 3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder
3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder モーションキャプチャーシステム Xsens MVN
モーションキャプチャーシステム Xsens MVN