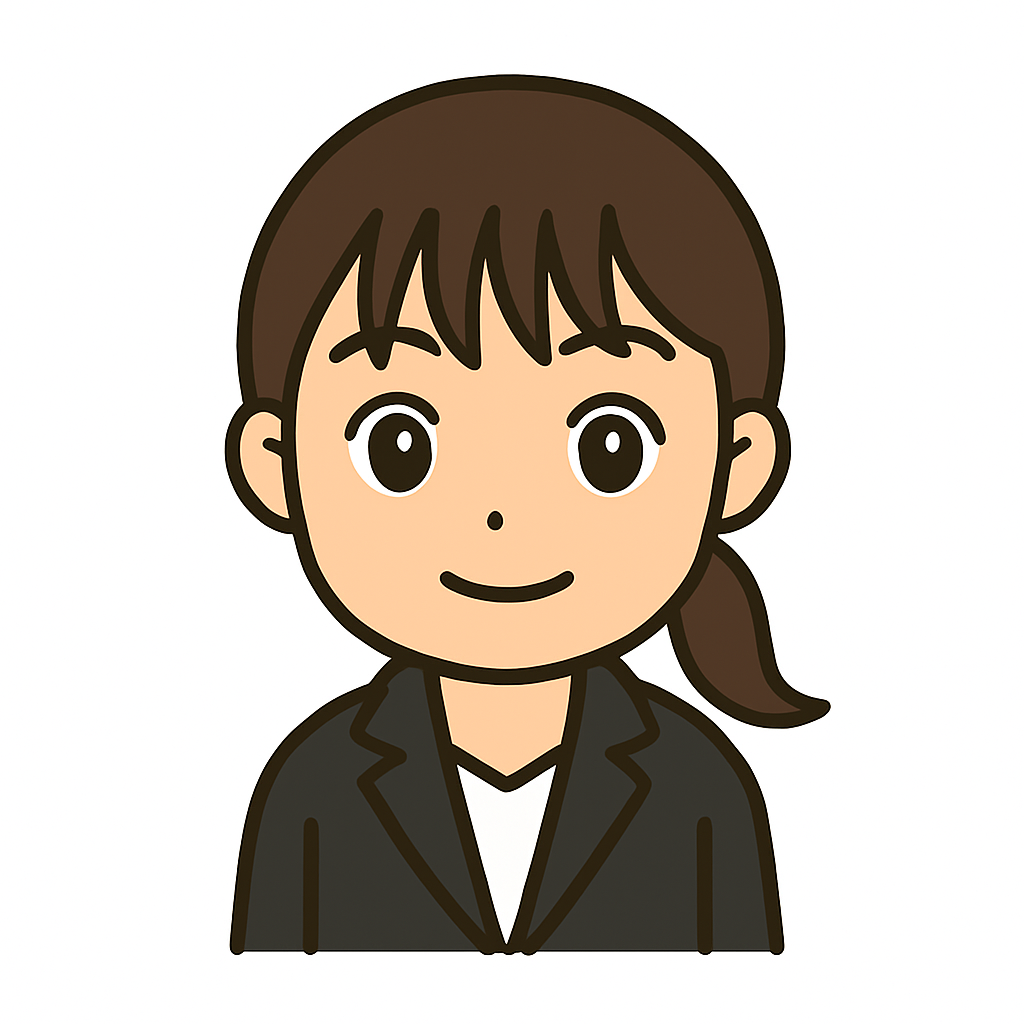こんにちは、丸月瑠奈です。設備の更新計画において、「過去の記録を基に適切な更新計画を作成したいけれど、データが見当たらない…」というお悩みの方も多いのではないでしょうか。機器の設置年、経過年数、点検や不具合の履歴、型式・容量、設置場所といったデータはとても重要でありながら、フォルダや紙、メール、担当者の記憶に散らばっているため、現在の設備の状態を適切に把握しにくいのが現状です。結果、推測に頼るものになり、計画作成時間の増加や更新計画の精度低下に繋がってしまいます。今回は、こうした課題を解決するための「設備データの適切な管理方法」を実務的な視点から整理し、ご紹介します。
設備更新計画作成における課題
更新計画の策定において、以下の3点でつまずくことが多く見られます。
- データの所在不明:設備台帳はあるが更新されていない、経過年数のデータや作業履歴が担当者の個人記録や報告書、メールなどにバラバラに存在。
- データの粒度のバラつき:同一の設備でも、機器Aは詳細情報が整然と揃っているにも関わらず、機器Bは製造年すら不明というケースがあるため、比較ができず優先度が決めにくい。
- 横断で見えない:建物別・フロア別・機器種別でデータを並べ替える際に、Excelを跨ぐたび関数が壊れる。経過年数の一括算出も面倒。
これらの課題が複合的に絡み合うと、「今年どの範囲で更新するのか」「必要な予算はいくらか」という問いに対して明確な答えを導くことは難しくなります。その結果、現場はその場しのぎの対処に追われ、管理側は後手に回り、オーナーは不安を抱くという悪循環に陥ります。
散在するデータにより発生するリスク
データが分散・未整備のまま進めると、以下のようなリスクがあります。
- 故障の同時多発:経過年数の偏りを把握できず、同一系統が同時期に故障することで、繁忙期の機会損失は甚大化。
- 投資の後手化:更新優先度が曖昧で、延命修理を重ねた結果、最終的にコストがかさんでしまう。
- 説明責任の弱さ:判断根拠が「経験則」に偏りすぎ、オーナー承認や監査対応に時間が必要となる。
- 安全・法令面の抜け:点検履歴が追えず、見落としからコンプライアンスリスクに発展する可能性。
計画はスピードも大切ですが、根拠の透明性を欠くと、無駄なやり直しが多発します。更新計画の肝は、最新で正確かつ横断的に比較可能なデータ基盤の整備です。
DK-CONNECT BMで設備データを一元管理
ダイキン工業が提供するDK-CONNECT BMでは、データ基盤を整え、更新計画におけるボトルネックを解消します。以下の3つのポイントがあります。
-
クラウド一元管理で「最新がひとつ」
設備の基本情報(型式・容量・設置年・など)から詳細仕様、修理履歴までをクラウドで一元管理できます。これにより、情報の分散を防ぎ、履歴の蓄積により判断が容易になります。「どこに何がある?」「いつ何をした?」といった情報の探索にかかる時間を大幅に削減することができます。
-
フロアマップからすぐに設備情報にアクセス
フロアマップ上で設備位置を確認し、ワンクリックで該当機器の情報にアクセスできます。現場で直接確認し「この位置のこの室内機ね」と即情報にアクセスできるため、データの蓄積や閲覧もスムーズに行えます。
-
絞込検索で“優先順位”を確認可能
経過年数、機器種別、型番、製造番号、フロアなどで柔軟に絞込検索が可能です。例えば「10年以上経過×パッケージエアコン×1F」のように条件をかければ、更新候補がすぐに抽出できます。さらに、機器ごとの故障・不具合の履歴も確認できるため、不具合の回数を基に更新機器の優先度も明確化できます。
これにより、設備機器の状態を見える化し、適切な更新計画作成をサポートします。
運用イメージ(おすすめの型)
- 定期点検や修繕のたびに履歴をDK-CONNECT BMへ登録し、「現場で更新・本部で即共有」を徹底。
- 四半期ごとに「経過年数×不具合履歴×重要度」で抽出し、候補群をレビュー。
- 合意資料は、台帳・履歴・抽出条件をそのまま根拠として活用でき、説明の短縮と、説得力を高めることが可能。
得られる成果
- 情報を探す手間を削減し、更新計画作成の時間を短縮。
- 一貫した根拠により、承認がスムーズ。
- 更新の先送りや重複した投資を抑制し、総コストを最適化。
- 現場、管理、オーナーが同じ画面で確認でき、意思決定の迅速化が実現。

 製造業向けITソリューション
製造業向けITソリューション 品質DX支援 QX digital solution
品質DX支援 QX digital solution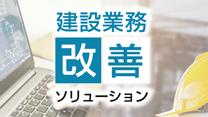 建設業務改善ソリューション
建設業務改善ソリューション ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM
ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM FILDER SiX TOP
FILDER SiX TOP FILDER SiX 電気 TOP
FILDER SiX 電気 TOP Rebro D TOP
Rebro D TOP 実験記録をデータベース化 ParsleyLab
実験記録をデータベース化 ParsleyLab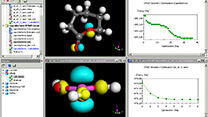 マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio
マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio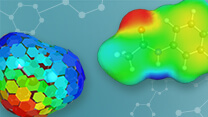 熱力学物性予測ソフトウェア COSMO
熱力学物性予測ソフトウェア COSMO 電子実験ノート
電子実験ノート 総合3DCG 制作ソフトウェア Maya
総合3DCG 制作ソフトウェア Maya 総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max
総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max 3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder
3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder モーションキャプチャーシステム Xsens MVN
モーションキャプチャーシステム Xsens MVN